第114回看護師国家試験 総評
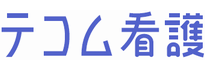
第114回看護師国家試験を受験された皆様、お疲れさまでした。
新カリキュラムに合わせた問題配列
…在宅看護論から地域・在宅看護論へ…
今年度は、過去問重視であり、適用3年目となる令和5年度版看護師国家試験出題基準に基づいて出題されていたように思いますので、出題基準の中からどんな問題が出題されていたのかをしっかり確認することが重要です。また、新カリキュラムで学習された学生さんが受験初年度となり、「地域・在宅看護論」の問題が新しく組み込まれ、出題基準の構成から変化して例年よりも若い番号で出題されていました。地域に暮らす全ての人たちを対象とした「地域・在宅看護論」を「基礎看護学」の次に位置付け、早い段階で学習させようというコンセプトが国試にも反映されたと言ってもいいでしょう。
5肢問題は選択に迷う問題が多く難化
…症状や日常のサービスを思い描いて知識を応用…
出題形式としては、5肢択1が15問(うち状況設定問題4問)、5肢択2が21問(うち状況設定問題5問)と合計数的には例年並みの出題でした(前回113回比5肢択1が6問減、5肢択2が3問増)。どちらも状況設定問題での出題が増加しています。今年度の5肢択1および5肢択2は、選択に迷う問題も多く難易度が高くなっているように感じました。症状をイメージしたり、日常で行われるサービスを思い描いたり、知識を応用して解答を導き出すことが求められました。
必修問題
…プール問題対策が重要だが、解剖・病態の深い知識が問われる問題も…
必修問題については過去問からの出題が多く解きやすかったのではないでしょうか。改めて、プール問題対策が重要だということが分かります。しかし、心室頻拍を心電図波形から読み取る問題(午前問題13)や心静止患者への投与薬剤(午前問題25)のように医師国家試験に出題されている問題、これまで必修での出題がなかった輸血用血液製剤の種類を問う問題(午後問題23)など、「人体の構造と機能」と「疾病の成り立ちと回復の促進」の深い知識が試される問題もありました。
…トレンドの少子高齢化は統計だけでなく社会情勢をみる広い視野を…
生産年齢人口の構成割合(午前問題1)、65歳以上の者がいる世帯の割合(午前問題10)、悪性新生物の部位別死亡数(午後問題1)、外来受療率で最多の傷病(午後問題2)のように、少子高齢化による近年の変化が問われる問題も多くなっていますので、統計だけではなく社会情勢も合わせて視野の広い学習が必要です。看護師のボディメカニクス(午前問題20)についても出題されており、基礎看護技術として、働く看護師の安全・安楽も見直さなくてはなりません。
一般問題
…短文事例が減少、地域・在宅看護関連が増加、臨床系は症状・検査・薬物作用が出題…
一般問題も過去問からの出題が多くみられましたが、どの領域からも満遍なく疾患における症状や検査、薬物の作用、その対応の問題が出題されていました。今年度は短文事例問題が少なく、高齢者虐待防止法(午前問題57、午後問題29)や地域密着型サービス(午前問題58)、障害福祉サービス(午前問題87)、日常生活自立支援事業(午前問題89)、介護保険法(午後問題86、87)など高齢者看護、地域・在宅看護に関する問題が多いように感じました。人口動態統計(午後問題55、80)も高齢者に焦点が当たっており、少子高齢化社会における課題を知っておくと同時に法的根拠と社会保障制度を関連付けて覚えておくとよいでしょう。
…言葉だけでなく、内容の把握が大事…
難しく感じやすい人名・言葉や理論では、フィンクの危機モデル(午後問題31)、ストレングスモデル(午後問題54)、ピアジェの認知的発達段階(午後問題60)、ダイバーシティ(午前問題34)、プレコンセプションケア(午前問題66)が出題されていました。危機への適応過程やストレングスモデルの6原則、認知発達の4段階、患者さんの個別性の理解、妊娠前からの健康管理について、言葉だけではなく内容をきちんと把握しておくことが必要です。また、看護記録(午前問題75)、看護部組織図(午後問題71)、プライマリナーシング(午後問題72)は看護師として働くときの責任と役割に関連しますので学生のうちから捉えておきましょう。
計算問題、画像・図形問題
…計算問題は定義の理解が解答の手助けに…
計算問題はBMI(午後問題90)、肥満度(午後問題103)、分娩所要時間(午後問題109)でした。算出方法だけではなく、それぞれの定義を覚えておくことが解答に役立ちます。
…画像・図形問題はイメージしながら視覚的に覚えることが必要…
画像・図形問題は、別冊以外に問題の中でイラストやグラフとして出題されたものが10問ありましたが、過去の類似問題や看護実践での場面の想起から解答を導き出せますので、心室頻拍(午前問題13)や長期臥床患者のポジショニング(午後問題19)の初出問題に関しても、活字の説明文や選択肢だけでなく、イメージしながら視覚的に覚えることも必要となります。
状況設定問題
…問題文中の情報を正確に把握しアセスメント能力を高める…
状況設定問題は、過去問で出題されている疾患が多くみられました。患者さんの現病歴やデータ、現在の状況を読み取り看護判断を求められる問題が増えていますので、疾病の病態の理解とともに、症状、検査、治療、その時の看護師の対応や看護ケアについてしっかりと学び、知識として定着しておくこと、また、問題文中の情報を正確に把握することが重要です。複数患児の診察の優先順位決定(午前問題106)や今後の予測に基づく判断(午後問題95、午後問題113)といった出題もあり、アセスメント能力を高めることも必須です。
…「災害看護は必ず出る」と思って臨もう…
午後問題には、今年も災害時の問題が出題されており、一般問題午前77、午後問題74と合わせて災害時に起きやすい疾患や心理的変化、災害時の対応と看護、感染の集団発生防止、心のケアについて捉えておきたいものです。災害看護の問題は必ず出題されると思って対策しておくことをお勧めします。
…状況設定問題対策のキーワードは“読み取る力”…
出題の問いかけや選択肢の文言は注意深く読まないと問題の意図がわかりにくいことがありますので、問題をよく読み、持っている知識を総動員して考えることも大切です。
今後も、看護判断能力や看護実践能力を問う問題が増えると予想されますので、情報を整理してアセスメントしながら患者さんの状況をしっかりイメージし、長文やデータを読み取る力を付け、国家試験に臨むことが大切です。
![TECOM[テコム]](/html/user_data/assets/images/common/logo.svg?ver=2)